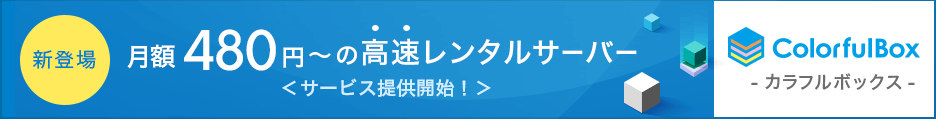|
改訂 火魅子奇譚八帝伝 序章 (H:小説版 M:九峪・その他 J:基本シリアス) |
- 日時: 12/06 13:41
- 著者: 青樹
- 火魅子奇譚 八帝伝
序章
穏やかな日差しの入り込む廊下を一人の男が歩いている。ざんばらに切られたその髪形、
比較的整った顔立ちをしているが、その肌は少し日に焼け、ひ弱そうと言うよりは精悍と
いったほうがいい。
黒い上着は右鎖骨の前で留められ、腰の若干下までスリットが入っている。我々の世界
で言うところのパオ(中国の拳法着、映画酔拳でジャッ○ー・チェンの着ていた裾を腰帯
に挟むアレ)に酷似している。それに袴の様な大き目の黒いズボンを合わせている。
普通大き目の服を着て歩けば、衣擦れの音が少しでもするはずなのだが、彼は音を立て
ていない。ただそれだけのことなのだが、そのことこそが、彼の「武」の練りこみ具合を
語っていた。
此処は五天世界の外にある世界、「第六天・神界」。五天に生きるものには知られていな
い。だが、確かに第六天は存在したのである。ただし、我々の世界に生きた、かの織田信
長が呼び称された「魔王」の如き者を出現させる世界ではない事は確かである。
無論、神界にも其処に住む人々の営みが有り、それは我々と何ら変わることはない。敢
えて違いを挙げようとするのなら、身体的・精神的強度が格段に強いということであろう
か。
彼はふと、日の降り注ぐ庭へと目を向けて立ち止まった。今、この世界は実に穏やかだ。
だが、かつてこの世界から汚い陰謀により追い出され、記憶と力を閉じられて遥か時空の
彼方へと消えたアイツはどうしているのだろう。
彼は弟のように思っていた青年のことを思い出した。その眼は此処ではないどこか遠く、
はるか記憶の彼方を見ているようだった。
「九峪・・・・・・、元気でやっているか?」
彼はそう呟いて少しの間、空を見上げていた。不意に彼は後ろを振り返り、虚空へ向け
て話しかけた。
「榛奈(はるな)か、どうした? お前らしくも無い、気配が漏れていたぞ」
彼の前で一陣の風が吹き、短い赤髪の下に額当てをした少女が跪いた姿勢で姿を現した。
額当てのせいか、彼女の表情を窺い知ることは難しかった。
「申し訳御座いません。火急の用件で御座いまして」
「ほう、聞こう」
「はっ。只今、第三天の物見より時の御柱が動き、天穴が開いたとの報が届きました」
だが男の表情に何ら変化は見られなかった。むしろつまらないといった風さえ見受けら
れる。
「で、何か気になるものでも出てきたか?」
少しの間の後、榛奈は幾分声を潜めて答えた。
「・・・・・・炎龍帝、九峪雅火古様。御帰還に御座います」
ここで初めて男の表情に変化が表れた。驚きと、そして若干の喜びが混じった顔。そし
て男は笑い出した。さも可笑しそうに、腹を抱えて。
「フッ、フッフッハッハッハッ! そうか! アイツめ、生きていたか」
「? 八色(やくさ)様、何がそのように可笑しいのですか」
「可笑しいのではないよ、榛奈。俺は嬉しいんだ、悪運の強い弟分が誇らしいんだよ」
「はあ、左様で御座いますか・・・・・・」
八色はひとしきり笑った後、榛奈の目を見据えて他の者に伝えたかを問う。
「いえ、まだ報告しておりませんが・・・・・・」
「よし、ならば緊急会議を開く由、他の六帝に伝えよ。俺は議の間にて待つ!」
「ははっ」
榛奈が現れた時と同じように、風とともに姿を消す。八色はそれには目もくれず、もと
来た方向へと踵を返した。彼の執務室と、会議の場となる議の間は正反対の方向にあった
のである。
議の間への道すがら、離れにある武具殿から奇妙な音が聞こえてきた。それはまるで龍
の鳴き声によく似て、焔の立ち昇る轟という音にも聞こえた。
(ほう、龍炎め、九峪の気紋を嗅ぎ付けたか。流石は龍武一の荒(すさ)ぶり、か)
八色はただ、ニヤリとしただけでその場を後にした。
さて、八色が今いるのは神界にある政府、その中でもとりわけ極東の島国の南方守護を
担当している、八大龍帝と呼ばれる者達の執務殿である。
本来、神界に住まう者たちは五天世界を監視する任に当たっている。その内、人界担当
上位八神の部下として彼らは主に人界の監視を行っていたのである。
先程の武具殿より少し北に進むと、いかにも重厚そうな両開きの扉が八色の目に映った。
その扉を開けて暗い廊下を進むと、微かな光が漏れていた。光の漏れている部屋へと八色
は足を踏み入れた。その瞬間、部屋は眩いばかりの光に照らされる。此処こそが、議の間
『天晃』であった。
其処には既に彼以外の六帝が集結を果たしていた。皆、八色と同じ服装をしている。違
いを挙げるならば、それぞれの胸にされている昇龍刺繍の色が違うということだろうか。
上座に座る女性は黄金色、その両隣は空席で、時計回りに暗灰色、青海色、白銀色、紫紺
色、翠緑色の錦糸で刺繍がされた服を着込んだ男女が座っていた。
「随分早いな、さっき遣いをやったばかりの筈だが?」
そう言って八色は、上座に向かって左側の席に腰を下ろした。それを見て彼の右に座っ
ていた女性が口を開いた。
「貴方が遅いんでしょう? 何処で道草を食ってきたのかしら」
その一言に彼は苦笑しつつも、一度皆を見回してから事の次第を話し始めた。
此処で時間軸は少し遡る。
彼は余りの眩しさに目を覚ました。鬱葱と茂った木々の間、丁度日の当たるところに頭
が位置して倒れていたようだ。
「こ、此処は・・・・・・? 何処だ?」
頭の中が、霧がかった様な感覚で埋め尽くされている、気持悪い。そんな気分の彼に後ろ
から声を掛けた存在があった。
「あれえ? 何でキミが?」
ボーイソプラノのような高いトーンの声がする。はっとして後ろを振り向いた彼の目の
前には妙な生物が宙を漂っていた。
彼がそれを目にしたときだった。一瞬の間の後、青年は突然絶叫した。
「・・・・・・うっ、うわぁああああああああああっ!」
「わぁっ! な、なに? どうしたのさ。ねえ、チョット!」
膝を地に付いて荒く呼吸を繰り返す青年を目の当たりにして、空中にプカプカと浮かぶ
不思議生物は、ただオロオロとするばかりで何をするでもない。
「も、もしかして狂っちゃったのかな!? やっぱ一般人には・・・・・・」
(俺は・・・・・・俺はどうなった? 確か俺はヤツとやり合って・・・・・・異世界へ、転生した・・・・・・?)
目まぐるしく、頭の中で様々な映像がフラッシュバックする。剣、少女、八匹の龍、人、
赤子、男、雷、遺跡、学者、技、力、学校、世界、そして鏡。一通りの知識がただ痛みと
なって過ぎ去る。
(ここは・・・・・・、また違う世界・・・・・・か? いや、さっきのアレは天穴だよな)
彼は何かを求めるように天空を振り仰いだ。そして汗だくになりつつも、荒い息の下か
ら好き勝手に呟かれる不思議生物の言葉に反論した。
「俺は、狂っちゃ、いねえよ・・・・・・、少し調子が、悪かっただけだ」
かの不思議生物は顔の前まで漂ってきて、青年を覗き込む。
「えっ? ・・・・・・そうは見えなかったけど」
「大丈夫だ・・・・・・。で? 一体お前は何だ? 此処は? 何で俺は此処に居る」
青年は幾分落ち着いてきたのか、周りを見渡しながら問いかけた。その問いかけに、不
思議生物は申し訳なさそうに、ここが三世紀の九『洲』であることを明かした。因みに、
この不思議生物の名はキョウというらしい。
(予想は当たりか、第三天だな。よりにもよって、九洲とはなあ)
答えることなく考え込みだした青年の顔をキョウが再び覗き込む。
「ねえ君、ホンっとに大丈夫?」
「あ? おう、俺は九峪ってんだ」
九峪が名乗ると、キョウは品定めをするように九峪を見た。それはもう舐めるように。
「んだよ? 何かおかしいとこでもあんのか」
キョウは「そういうわけじゃないんだけどね」とだけ言って、起用に短い手足を組んで、
空中で考え込んだ。
(何でこんな一般人がこっちに来ちゃうかなぁ~。せっかく日魅子を見つけたのにぃ)
「おい」
九峪が呼びかけるが、キョウは同じポーズのまま空中でフヨフヨ漂っている。何度呼び
かけてもシカトし続けるその態度に、九峪はキョウをガシッと掴んだ。
「コ・ラ! 貴様、他人様を勝手に連れてきておいてシカトか? 用がねえんならとっとと
返しやがれ!」
「うっわぁっ! ぐ、ぐるじい・・・・・・きゅぅ」
あまりの衝撃にキョウの意識が軽く飛んだ。しかし、非情にも九峪は首も折れよとばか
りにズビシッとデコピンを食らわす。
ビクッと反応したキョウが目を覚ますや九峪の手を抜け出した。
「はっ!? ひどいじゃないかぁ! 九峪は僕を殺す気なのぉ!?」
「やかましい。俺をシカトするからだ。で? 俺を返してくれんのかよ」
人形のようなファンシーな手を、腕の前でつんつんさせながら申し訳なさそうに、キョ
ウは不可能であることを告げた。
「(だろうなぁ、そう簡単にゃアレ、開かねえし)んだとぉ!? じゃ、どうすんだよ!」
九峪は敢えて何も知らないふりを装って焦ってみせた。今ココで、キョウに事情を話す
のは容易い。だが、神界のことを話して無闇に頼られることは避けたかった。
今の九峪はかつて神と呼ばれる存在だったころの記憶を持つ、『ただの』高校生に過ぎ
ない。力の無い今、力を持つ存在であると僭称することは、避けるべきであるし、九峪自
身も嫌いだったのだ。
「わわっ! ストップ、ストぉーップ!! ま、まあ、手段が無いことも無いかな」
(ふーん、そんなはずは無え。時の御柱は、そうそう簡単には動かん。まあ、聞くだけ聞い
といてやるか)
「そういうことは早く言え! んで、どうしろって?」
「えっとね、耶麻台国の女王火魅子ならそれが出来ると思うよ」
九峪は声をあげて大仰に驚いた。
「邪馬台国だぁ!? 卑弥呼だぁ!? じゃあ此処はマジで3世紀の日本だってのか!?」
「う~ん、九峪が知ってる歴史とは若干異なってると思うよ。ホラ、九州じゃなくて九洲
だし、邪馬台国も耶麻台国、卑弥呼も火魅子だからね。地形も少し違うし、まあ一種の
パラレルワールドって所カナ」
キョウが小さな手で小枝を支えながら地面に文字を書き、九峪に違いを示した。
「じゃあよ、その火魅子様ってのは何処に居るんだよ?」
「居ないよ~ん」
まるで他人事のようなキョウの物言いに、さすがの九峪もカッチーンときた。
(むかぁっ! こいつ人様の事、舐めてんのかよ)
「とりあえず、いっぺん死ね!」
キョウの首と思しき部分を、九峪が指で締め上げた。見る見るうちにキョウの顔が赤か
ら紫へ、そして青く変色していく。余程綺麗に極まったらしい。
「わっ! わぁっ! ぢょっ、ズドッブぅぅ~っ!! お願いだがら・・・、ぞの手を、放じぃ
でぇぇ~っ」
「なんだ? 遺言など、聞く耳もたんぞ」
そう言いながらも、九峪はとりあえず手の力を緩めた。
「そ、そうじゃなくって。あのね、今、耶麻台国は狗根国に滅ぼされてしまっているの。
でもね、次の火魅子候補の女の子達が各地に散っているから、その子達の誰かを探しだ
して、女王に即位させればいいのさ」
その話を聞いて、九峪はキョウを解放した。
「じゃあ、その子を見つけちまえば俺はすぐにでも帰れるって寸法な訳だ」
「それがね、そうもいかないんだ」
幾分悲しみを含んだ声でキョウが言った。だがその裏にはどうも別の考えが見え隠れし
ているのが九峪には見えた。キョウは程よく大根役者だったのである。
「あのね、火魅子即位には王都耶牟原城の開放が必要なんだ。それというのも其処の神殿
に宿っている姫神子様の力を授かって初めて女王に成れるんだ。だからそう簡単にはい
かないんだよ・・・・・・」
縋る様な視線をチラチラと九峪に向けるキョウであったが、九峪には既にキョウの考え
は読めていた。
復興させれば帰れるとか何とか言っておいて、復興させた後で「実は嘘でした」と言う
つもりなのだろう、と。
(とぉころがどっこい、そうはイカの金隠しってな)
妙なところで考えが古い九峪である。今時、こんなこと言う人はいないであろう。
「おい、キョウ。本当に火魅子とかいうのが時の御柱ってのを動かせるんだろうな? も
し復興できたとしてさ、その後で『やっぱり無理です』なんてのは、納得出来んぞ」
キョウは思う存分ギクッとした態度で体中に大粒の汗を掻きだした、九峪の予想は間違
ってはいなかったどころか大当たりというところである。
まあ、実のところ九峪にはキョウが望むようにするつもりは『それなりに』有った。力
が無い以上、今の彼はただの人。このまま突っぱねて、どこぞで野垂れ死ぬよりかはマシ
なのである。
「お前、解かり易すぎだろ。大根役者にも程があるっての」
九峪が頭の後ろで手を組み、呆れたようにキョウを見下ろした。そのキョウは、後ろを
向いていじけた様に膝を抱えていた。
「まあ、いいさ。お前の考えに今は乗ってやるよ。野垂れ死ぬのもゴメンだからな」
「へ? いいの、ホンとに?」
キョウの問いかけには答えず、九峪は銅鏡を拾うとスタスタと歩き出した。
「おら、さっさと来いよ。どこ行きゃいいのか判んねえだろ」
振り返らずに歩いていく九峪の後ろを、キョウは笑顔で追いかけるのであった。
「待ってよ、九峪ぃ~! 向かうならアッチだよぉ~」
「・・・・・・と、まあこんなわけだ。炎龍帝、奇跡の帰還ってヤツだな」
八色が説明をそう締めくくると、その場に居た者の視線が自然と今空いている席に集ま
った。
「じゃあここで九峪が置かれている状況をおさらいしておこうか」
そう言って後ろに控えていた榛奈を顧みる。
「はい、それでは説明させて頂きます。これまでの調査によりますと、どうやら耶麻台国
の祭器、天魔鏡の精に間違って連れて来られたようですね。さらにこちらに戻ってこら
れた時に生じた、何らかの衝撃で記憶の封印も解けていらっしゃいます」
其処でやっとこさ、上座に座っていた女性が口を開いた。
「それで? あなたはどうしたいのかしら。まあ、あなたのことだから、どうせよからぬ
事を考えているんでしょうけれど」
「連れないねぇ、ま、そんなとこだ。で、俺から提案したいのは、各種装備の使用許可及
び九峪の援護だな」
八色の言葉に、暗灰色の昇竜刺繍をした服を着た、長髪の青年が補足を加える。
「そうですね、最近人界の様子がおかしい。私は雷龍の意見を支持します水龍、鳳龍はど
うですか?」
青年が、自身の隣と八色の横に座る女性二人に問いかけた。
「いいんじゃなぁい? 私は問題ないわぁ。 問題は鳳龍のねぇねでしょぉ」
おっとりとした喋り方の少女が眠たげな目で、自分の目の前に座る女性を見た。その彼
女は、右肩の前にたらした三つ編みを弄んでいたが、話しの矛先が自身に向くと腕を組ん
で答えた。
「別に・・・・・・異論は無い。今のところ仕事も無いし・・・・・・。降りれるなら私も早めに降りる」
この言葉に残りの二帝、黒龍と白龍も同意し、会は滞りなく進んだ。九峪の補佐は次点
優先事項とされ、先遣として降りるのは発案した八色とされたのであった。
外されていた運命の歯車のひとつが、再びはめ込まれた。これが、この地において長きに
渡る戦乱の始まりであろうとは、人ならぬ神にすら未だ知る者はいなかった。
続く
| |