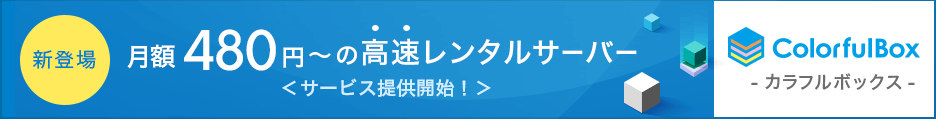|
火魅子伝改(改訂版) 第三話 恋する乙女(?) (H:ALL M九峪・清瑞・伊雅・兎奈美 J:平和) |
- 日時: 06/06 09:55
- 著者: 矢野 晶
<akirada@hotmail.co.jp>
- 伊雅と清瑞と会った次の日。
日はまだ半分も昇っていないが鳥の囀りが朝を伝える。静かで清々しい朝を壊すような
荒々しい足音と共に昨夜に話した女性…清瑞が現れた。
「く、九峪!!貴様なぜ交代の時に起こさなかった!!」
夜の番は交代が基本である。
それにも関わらず九峪は一人で番をしたのは一般的にも悪い事なのだが、九峪の場合は
神の使いと言われる立場なのだ。
そして自分達がノウノウと寝ていた事は万死に値する…清瑞も日頃なら途中で起きて様
子をみたりするのだが1日中走って、九峪の罠を掻い潜った疲労は並大抵のものではなか
った。
伊雅も同じである。
でも寝る前に清瑞は言っていたのだから起こさなかった九峪が悪い。
「おはよう。別にいいじゃないか、清瑞だって疲れていただろ?」
いつもの九峪スマイルが清瑞の怒りの矛を綺麗に受け流す。
「おはようござい…い、いや、そそそんなに笑顔で言われてもゆる―」
「朝ご飯できてるからな、伊雅とキョウを起こしてきてくれ」
(何か間違ってる!あなたはきっとどこかが間違ってる!そして私も…)
何処で何が間違っているのか考えるが答えはでなかった。
何やら腑に落ちないがとりあえず伊雅とキョウを起こしに行った。
清瑞が神社の中に入っていくのを確認すると九峪の座っていた位置から九峪の姿が消え
た。近くにある草むらが揺れる。
「そこで何してるんだ?」
その草むらの後ろに回りこんでそこにいた人物に話掛けた。
「お兄さん、なんでわかったの?」
恐ろしいほどハイレグで水着のように隠す場所だけ隠す様な服(?)を着た女性だっ
た。
「だって耳見えてたぞ」
九峪は苦笑いをしながら言った。九峪が言った耳は普通の耳ではなく兎の耳だった。
女性は、ああ忘れてた!と言った顔だった。
「んで、見るからに普通の人じゃないあなたは何者だ?」
「ん~と、魔兎族の兎奈美って言うんだけどね~一応魔人やってま~す」
(魔人は辞められるものなのか?)
そんなくだらない事を思いつつ、九峪は警戒してポケットにあるナイフを握っている。
魔人相手に何処まで通じるかは、さておきとりあえず事情を訊いてみた。
「その兎奈美さんは何をしてるんだ?」
「餌探してたんだ~」
「……………人参?」
「違うよ~…大好物だけど」
(やっぱり、そうなんだ)
「餌ってのは…人間の事よ」
そう言った瞬間、九峪の視界から兎奈美が消え、いつの間にか出した兎奈美は武器らし
き物を手に持って九峪の後ろに回りこみ、斬りつけようとした…その時。
そして姿は再び消えた。
「なによこれ~」
声が聞こえたのは頭上3mほど上で木にぶら下がった状態でいた。
「それは、こういう時のためにさっき作った罠だ」
兎奈美は、それを聞いて愕然とした。実は背後をとられたのも驚きだったが、まさか罠
まで仕掛けているとは誰も思いもしないだろう。
「お腹空いてるなら一緒に朝食でもどうだ?」
兎奈美はまたしても愕然とした。まさか朝食に誘うとは思わなかった。しかも魔人をだ。
(けど、お腹空いたな~)
少々考えたが、やはり空腹には勝てなかった。
「じゃあご馳走になろうかなぁ」
「わかった」
現代人ではあり得ない位に自然と懐からナイフを取り出し兎奈美に向かって投げる。
兎奈美は突然の事で反応を示すが必要なかった。
ナイフは兎奈美の足を捕まえていた縄切り、兎奈美は縄から開放され落下してするバラ
ンスをとろうと試みたが上手くいかず、頭から落ちる。
お腹が空いていたのが原因だ。
(やば!)
兎奈美は、目を瞑って衝撃が来るのを待った…衝撃は来たが痛くはない。
不思議に思い目を開けてみると九峪がお姫様抱っこで受け止めていた。
「大丈夫か?」
九峪は少し焦った表情で見ている。
「焦るぐらいならもうちょっと丁寧に降ろしてよね」
兎奈美は笑いながら九峪の目を見ると本当に心配しているのが分かる。
(魔人なんだから落ちても大丈夫なんだけどね)
会って間もない、しかも魔人相手に真剣に心配する人間が、この世にいるとは思わなか
った。
もっとも「この世」には居なかったのだが…先日までは。
兎奈美は初めて男に好き…と言っていいほどの好意を抱いた。
「も、もう大丈夫だから降ろしてください」
「ああ、わか…」
九峪は殺気を感じ兎奈美を抱いたまま木に隠れた。九峪が元居た場所に苦無が突き刺さ
る。
「九峪…なにをしている」
清瑞だ…明らかに怒っている声で初めて会って脅された時より怖く感じる。
「お、俺が作った罠に掛かった人を助けていたんだ!」
眉毛をあげ、頭上をみて納得したようだ。
「ああ、なるほど」
清瑞は納得は…したが不愉快そうな顔は治っていなかった。
九峪は何処からともなく出した鞄の中からタオルを出して兎奈美に渡した。
(魔人だって事がバレたら説明が面倒だから、とりあえずこれで隠しててくれ)
(わかった…ありがと)
九峪と兎奈美は木の陰から出た。清瑞は兎奈美を品定めするように足元から頭まで見回
した。
「…いかれた格好ですね」
清瑞は、軽蔑するように兎奈美を見た。
(人の事は言えるんだな…自分も結構…)
九峪はつい口走りそうになったが心に留めておく事に成功した。
「こ…の……餌…ぶ…ん…ざい…で…」
兎奈美は怒りで暴走しそうだったが九峪がいる前でそうそう暴走する事はなかった。
恋する乙女(?)の弱みをヒシヒシと感じる兎奈美であった。
「清瑞、そんな事言てはだめだ」
少し怒ったような口調で清瑞をたしなめた。
「はっ、申し訳ありません」
その僅かな変化に気づいて清瑞は慌てて謝った。
「すまない…許してやってくれ」
「…いいよぉ、気にしてないから」
兎奈美にばかり気を使うの事に不満があったが自分に非があるので何もいえなかった。
まだ許しきってはいなかったが九峪がせっかく気遣ってくれているのを無下にするわけ
にはいかない。
「さてと、そういえば俺達の自己紹介がまだだったな、俺は九峪。耶麻台国を復興させる
為に神からの命を持って降り立った神の使いだ…一応」
兎奈美は目が飛び出さんばかりに驚いていたが最後の一応って部分だけ気になったが今
は無視。
「こっちが昨日から仲間になってくれた清瑞だ」
「どうも」
まだ不機嫌な清瑞だが挨拶は返すところを見ると少しは機嫌が直っているようだ。本当
に不機嫌ならおそらく無視もしくは塵でも見るかのような視線のどっちかだろう。
「んで、こちらは兎奈美さんと言ってさっきも言ったが俺が作った罠に掛かってるのを助
けた」
「よろしくね~」
こちらは怒気を収め調子が戻っている。
「兎奈美さんはなぜこんなところに来たんですか?」
「う」
兎奈美は唸った。言い訳を考えてなくて詰まるがすかさず九峪がフォローを入れる。
「兎奈美さんがいたあたりには食料がなくなり困って廃墟となった神社付近なら誰もいな
いから何かあるだろうと思って来たらしい」
確かに食料不足の村は数知れずあるから清瑞は特に疑問を持たなかった。
「と言う事なので朝食をご馳走する事にしたんだ。いいだろ?」
「…わかりました。元々九峪が用意してくれた食料です、私は口をはさめませんよ」
清瑞が苦笑しつつ答える。
第一九峪は神の使いなのである。一介の乱破に許可をとる必要なんて何処にもない。
(これから先、人の上に立つって自覚してるのか?…してないだろうな)
九峪の横顔を見ていると、これから先の苦難な道のりなのは分かっているが意外と簡単
な道かのように錯覚してしまいそうだ。
「じゃあ、とりあえず戻るか」
そして神社に向かって歩き出した。
伊雅とキョウは既に昨夜と同じ場所に座って待っていた。
「九峪~遅いじゃないか~何処に行ってた…の?!」
キョウは九峪に近寄ると青い顔になり身を少し震わせながらゆらゆらしている。
「九峪様…そちらの方は?」
「ああ、こちらは兎奈美と言って俺が作った罠…(以後略)」
「く、九峪!話があるからちょ、ちょっとこっちに来て」
話が終わるや否や空中で停止していたキョウは青い顔のまま九峪に神社の裏に来る様に
指で指し示す。
「食事の後でな」
それを蔑ろにするように取り合おうとしない九峪を見てキョウは焦ったように口が動く。
「そんな悠長な事言ってる場合じゃないよ。その兎奈美って子魔―」
「知ってるよ」
真実を語られる前に九峪は制止する。
「え!!!」
キョウはかなりびっくりしたのか宙をグルグル回っている。
(さすが天魔鏡の精だけあって見抜く力はあるんだな)
キョウの近くにより合わせる様に小声で話した。
(そりゃまあね…けど、分かってて食事に呼んだの?)
(あぁ、だってお腹空いてるんだぞ?誘って何が悪い?)
(いや…そりゃそうかもしれないけど…)
キョウの意見が普通だ、もし伊雅や清瑞に知れたら即戦闘になりかねない。
九峪はそれを望んでいないのをみると無駄な殺傷は控えろと言う事だと察する。
「キョウ様、九峪様いったいなんのお話をしているのですか?」
「いや、ちょっと気になる事があったんでキョウに聞いていたんだ」
「と、いいますと?」
「兎奈美から聞いたんだけど、この近くに魔人が出たらしいから、それに関してキョウと
何か対策を立てておく必要があるか、と言う事なんだけど…」
兎奈美は苦笑いしていた。自分の事を言っていると分かっているのだろう。
「なぬ!?魔人ですと!!」
「なに?!魔人だと!!」
伊雅と清瑞は同じような反応を示し周りに気配がないか探った。特に異常な気配はない
ので安堵のため息を付いた。
ここで付け加えると兎奈美ぐらいの上級魔人は並大抵の事では人間にはばれない。耳を
見せない事を前提とするが。
兎奈美に気づかなかったのは九峪が助けた相手だと言う事もあって対象に入っていなか
った事が原因である。
「さて、遅くなったけど、食事にしようか。ちなみにメニューはパンと野苺だ!」
気合を入れて言うが伊雅、清瑞、兎奈美の三人には何の事か分からなかった。当然であ
る。
「「パン??」」
「九峪、いつも思うけどどこからそんな物出してくるの?!」
「パン自体は作った。材料は鞄から出したけど。野苺はとって来た」
(胸を張って答えられても)
伊雅と清瑞、兎奈美は、まずパンの匂いを嗅いでいた。未知の食べ物だがカレーを食べ
た後の二人はさほど気にしなかった。見た目ではカレーの方がよほど異様だし匂いも独特
だったからである。
兎奈美は不思議そうにパンを突ついたりしている。
「食べ方は特にないけど、一口で食べれるぐらいに千切って食べるぐらいかな~」
「「はぁ」」
習ったとおり全員一口サイズに千切って口に運ぶ。
「柔らかくて匂いもいいですし食べやすいしとてもおいしいですな」
伊雅は絶賛すると清瑞、兎奈美が後に続く。
「ああ、これならいつでも食べれていいな。携帯食としても使えるんじゃないか?」
「これ、おいしいですよ~これの作り方今度教えてください」
二人とも気に入ってくれたようだ。それを食事には手を付けずに皆の感想を聞く九峪は
満足そうに笑う。
「そうか、よかったらこれも食べる?」
「九峪様は食べないのですか?」
「気にするな、俺は野苺だけでいい」
「わしは結構です」
伊雅はすでに満足して野苺をを食べていた。
「「私は貰おうかな」」
「「!!」」
兎奈美と清瑞は同時に欲しいと言った。その瞬間、兎奈美と清瑞との間に火花が見えた
ような気がした。
「二人とも…こういうやり方があるんだが…」
と言って半分に割って見せる。
「「な、なるほど」」
思いつかなかった。と表情が語っている。
二人の食べている姿を眺めて小さくため息をついた。
(この先こんな事でやっていけるのだろうか?)
そんな事を考えたが本心では全然心配していない自分の心がわかる。
「そうそう、これから先のことなんだけど…」
清瑞と兎奈美がパンを食べ終わって野苺に取り掛かろうとしていたが手を止めた。
「食べながらでいいから聞いてくれ。兎奈美はこれからどうするつもりなんだ?」
(このままついていくのもいいけど…)
九峪についていきたいという気持ちが大きいが重要な用事がある。
怖い怖い姉の顔が思い浮かび背筋に冷や汗を流して言った。
「申し訳ないですけど少し用事があるので、もう少ししたら村に帰ろうかな」
「わかった。伊雅と清瑞は?」
「もちろん私達は耶麻台国復興の為、九峪様についていきます」
伊雅も頷いて清瑞の意見に同意した。と言うか何を今更?といった風な表情である。
「わかった」
それから30分ほど話した兎奈美は里へ帰っていった。
とりあえず、神社の中で話す事にした。
伊雅と清瑞は凛々しい顔をしていた。それは初めてであった時の戦士の顔だった。
「これからの事なんだけど…まずは火魅子候補を探す、と兵士、物資の調達。諜報は欠か
せないだろうな…諜報は清瑞がいるから難しくないし兵士と物資は伊雅に昔の耶麻台国の
縁の者達に促すとある程度は手に入るだろう…問題はやっぱり火魅子候補かな」
伊雅と清瑞は目を丸くした。何も考えてないように見えて実は色々考えてるんだな。二
人は九峪の見る目を少し変えた。
ちなみに伊雅が耶麻台国副王である事はキョウから聞いている。
「はい、その通りです。火魅子候補を見つければ、すぐにでも行動を起こせるのですが…」
「伊雅が隠れていた里はどうなっているの?」
「里の人口は千人前後で兵士として使える者は六百人ぐらいです。物資…特に武器、防具
類は不足しております、食料は自給自足で蓄えだけで、千人ぐらいなら六ヶ月は食べるに
困らない程度はあります」
「他に使えそうな人材は?」
「女ではありますが音羽と言う者がいます。槍術ではわしでも勝てません。他に、これも
女ですが虎桃と言う弓を使わせたら九州一と言われる者います。他にも乱破で、まだ見習
いなれど優秀な者が二人います」
「そりゃ頼もしい」
九峪は笑顔で答えた。だが心の中では悲しんでいた。
(伊雅が敵わないほどの実力を持つ女の子か…いったいどれだけ苦しんだのだろう?人生
の選択もなかっただろうな…清瑞もそうだろう…)
清瑞の顔を見た。
(平然とした表情だが過去にどれだけ辛い事があっただろうか?どれだけ泣いたのだろう
か?)
そう思うと心が痛かった。
清瑞は九峪が自分を見ているのに気づいて、どうしたものかと言った感じで見つめ返し
てきている。
「もちろん、清瑞も随一の乱破ですぞ」
伊雅は妙な勘違いをしたらしい。それは疑っていないので訂正する必要はないがわざわ
ざ正す必要もないと判断してとりあえず頷く。
「もちろん期待してるよ、頑張っくれ」
「はっ!必ずや役に立ってみせます!」
今清瑞は耶麻台国復興軍の司令官、もしくはそれと同等の権力者と話をしているのだと
認識した。伊雅より上の立場の者など耶麻台国では、まずいない。しかも対等に…いやそ
れ以上に話している人物などいない。
「ただし命は大事にしろよ、死んだら何もならないからな。絶対に死ぬな!これは約束だ」
清瑞は愕然とした。乱破である自分に「死ぬな」と言われるとは思わなかった。
「わかりました。約束します」
清瑞は嬉しくてつい笑顔がこぼれた。自分をこれほどに思ってくれた事など今までなか
った。
伊雅は珍獣を見たような目で清瑞を凝視した。清瑞は乱破で感情は表に出さないように
訓練している。他愛ない会話で清瑞を笑顔にさせる九峪にも驚いた。
「もちろん伊雅もだ?わかってるな」
「はっ」
年甲斐もなく嬉しそうな伊雅。
「ところで軍師か参謀はいないのか?」
「武力に長けるものは数知れずいますが知力に長ける者はいません」
伊雅の今までの勢いがなくなり、顔を伏せた。
九峪はキョウが神の使いを名乗るように言った時からずっと考えた。自分が軍師や仮の
象徴になるとして、自分が活躍をして反乱が成功したら『火魅子』という象徴が薄れるの
ではないか、そんな疑問を抱いた。
(一時的にとは言え象徴となったら火魅子より神の使いを選ぶ奴らが出てくるだろう…)
ならやる事は大体決まってくる。そして出した結論は
「清瑞、俺の評価をしてくれ」
清瑞は何の事かよく分からなかったが、とりあえず思い浮かんだ事から言っていった。
「罠がかなり得意で武術もかなりの腕だと思う。頭に関してはまだ不明だ。ああ、後料理
が凄く上手だな。後…すけべ」
最後の評価は兎奈美をお姫様抱っこをしていた事に対してだろう。
だが最後の評価がこれから一番必要な物に近い物だった。
「そうか…清瑞や伊雅ならどんな上司が嫌?」
「そうですな…無能で強欲で自分の事しか考えないような輩ですな」
「私も同じようなものだ」
九峪の意図が見えないが、とりあえずと言った感じで答えた。
「伊雅と清瑞には話しておくよ。俺は戦術と武術、罠などに自信がある」
伊雅と清瑞は、頷いた。戦術は分からないが罠と武術…特に罠に関しては身を持って分
かっている。
「だが、あえて無能な…と言ってもあまり無能じゃ愛想つかされたら駄目だから無能より
はマシぐらいに無能な振りをするつもりだ」
二人は顔を見合わせ、九峪に視線を注ぐ。自分を無能に見せる事など普通はしない。
「な、なぜそのようなことを?」
「じゃあ、聞くけど二人は神の使いと火魅子どちらが偉いと思う?今は火魅子候補もいな
い状態だけどもし見つけて、復興が成功したら?」
伊雅と清瑞は唸った。神の使い…九峪がもし耶麻台国復興の鍵になるとしたら火魅子よ
り神の使いの方がいいと判断してもおかしくはない。
「ね?あまり神の使いの評価が高いと困るだろ?」
「「確かに」」
これを聞いては頷くしかなかった。
(そこまで先の未来の事を考えた事がなかった)
伊雅は九峪と神の使いという肩書きを利用しようと思っていたが思いを改めた。
「戦術とか政策は俺が何とかするから伊雅には俺の代わり指揮していって欲しい」
「はっ!!」
伊雅は平伏した。伊雅は九峪が完全に自分の上の立場であると認めた瞬間でもあった。
(この人なら復興軍の象徴として…いや、耶麻台国の象徴として居て欲しい)
九峪の予想した将来図は今も進んでいる事は、さすがの九峪でも分からなかった。
「清瑞、この事は秘密な」
「はて?なんの事でしょう」
清瑞はわざとらしく言った。それがあまりにもわざとらしく三人して一緒に笑った。
| |